園内マップ

-
太陽の広場レクリエーションゾーン
-
 小食土(やさしど)廃寺跡レクリエーションゾーン
小食土(やさしど)廃寺跡レクリエーションゾーン -
管理事務所レクリエーションゾーン
-
 冒険広場レクリエーションゾーン
冒険広場レクリエーションゾーン -
もみじ広場レクリエーションゾーン
-
市町村の森レクリエーションゾーン
-
石楠花(シャクナゲ)のみちレクリエーションゾーン
-
花畑レクリエーションゾーン
-
 サイクリングコース・第1・2サイクリングセンターレクリエーションゾーン
サイクリングコース・第1・2サイクリングセンターレクリエーションゾーン -
ローラーすべり台レクリエーションゾーン
-
展望広場・展望台展望ゾーン
-
辰ヶ台遺跡(たつがだいいせき)中央林間ゾーン
-
お花見広場中央林間ゾーン
-
 梅林中央林間ゾーン
梅林中央林間ゾーン -
紫陽花園・紫陽花のみち中央林間ゾーン
-
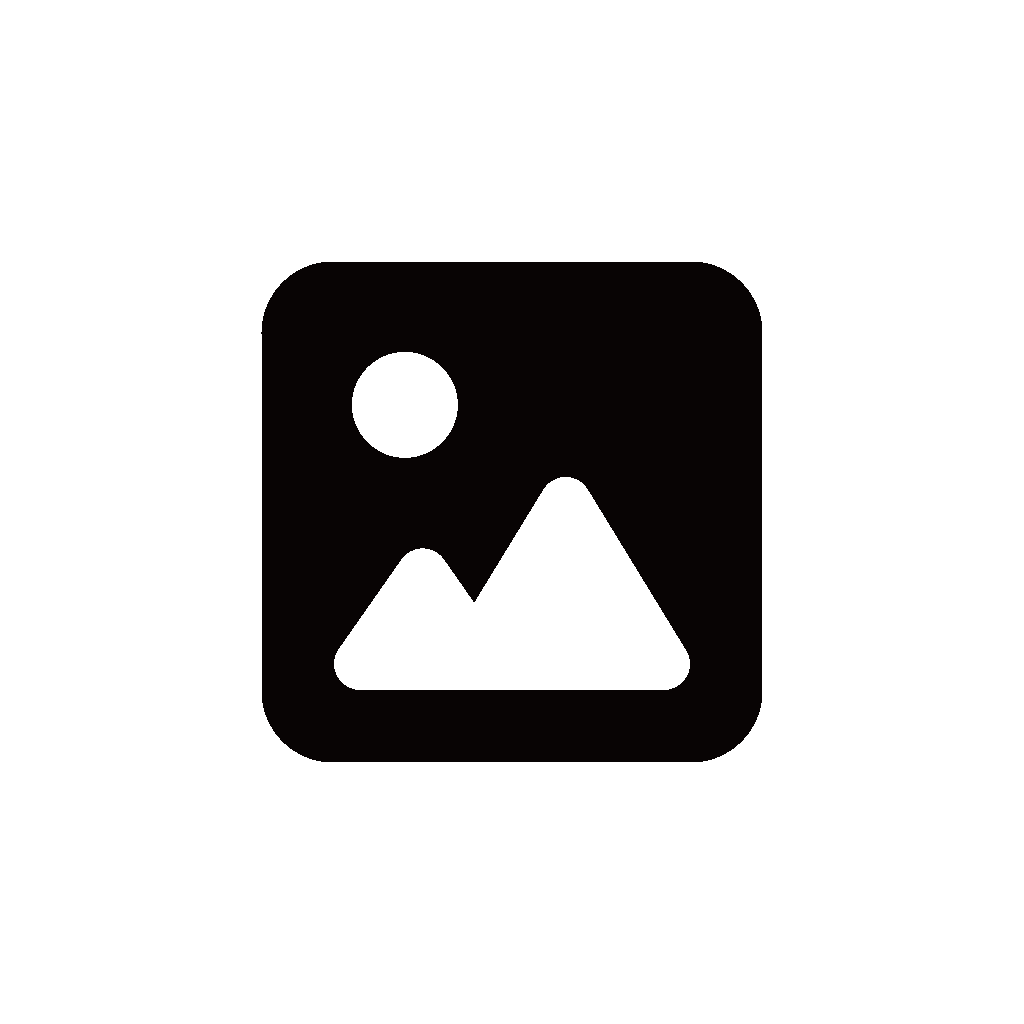 花木園中央林間ゾーン
花木園中央林間ゾーン -
下夕田池(シモンタイケ)中央林間ゾーン
-
竹林中央林間ゾーン
-
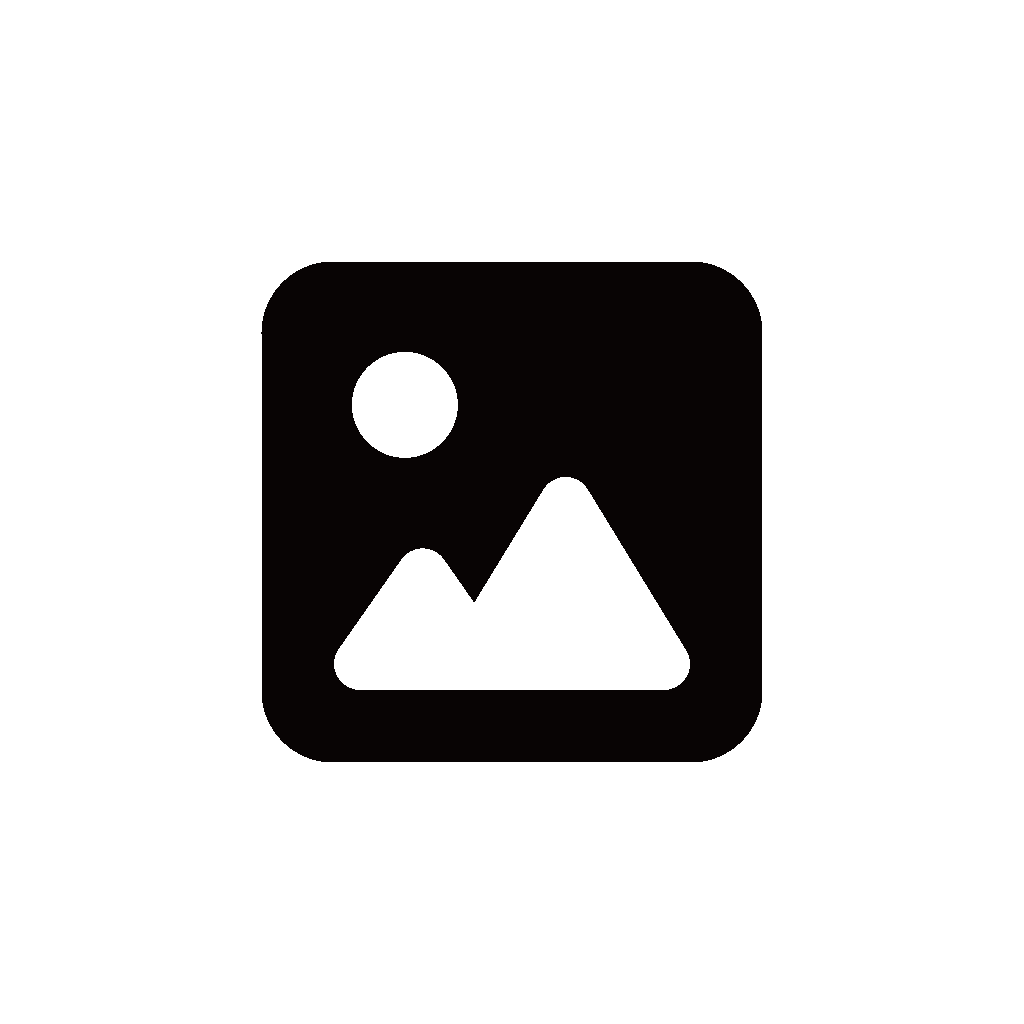 四季のみち中央林間ゾーン
四季のみち中央林間ゾーン -
春のみち中央林間ゾーン
-
秋のみち中央林間ゾーン
-
冬のみち中央林間ゾーン
-
萩のみち中央林間ゾーン
-
休憩広場中央林間ゾーン
-
展望園地中央林間ゾーン
-
テニスコート/野球場/サッカー場スポーツゾーン
-
多目的広場スポーツゾーン
-
疎林広場スポーツゾーン
-
昭和の森フォレストビレッジ宿泊・野外活動ゾーン
-
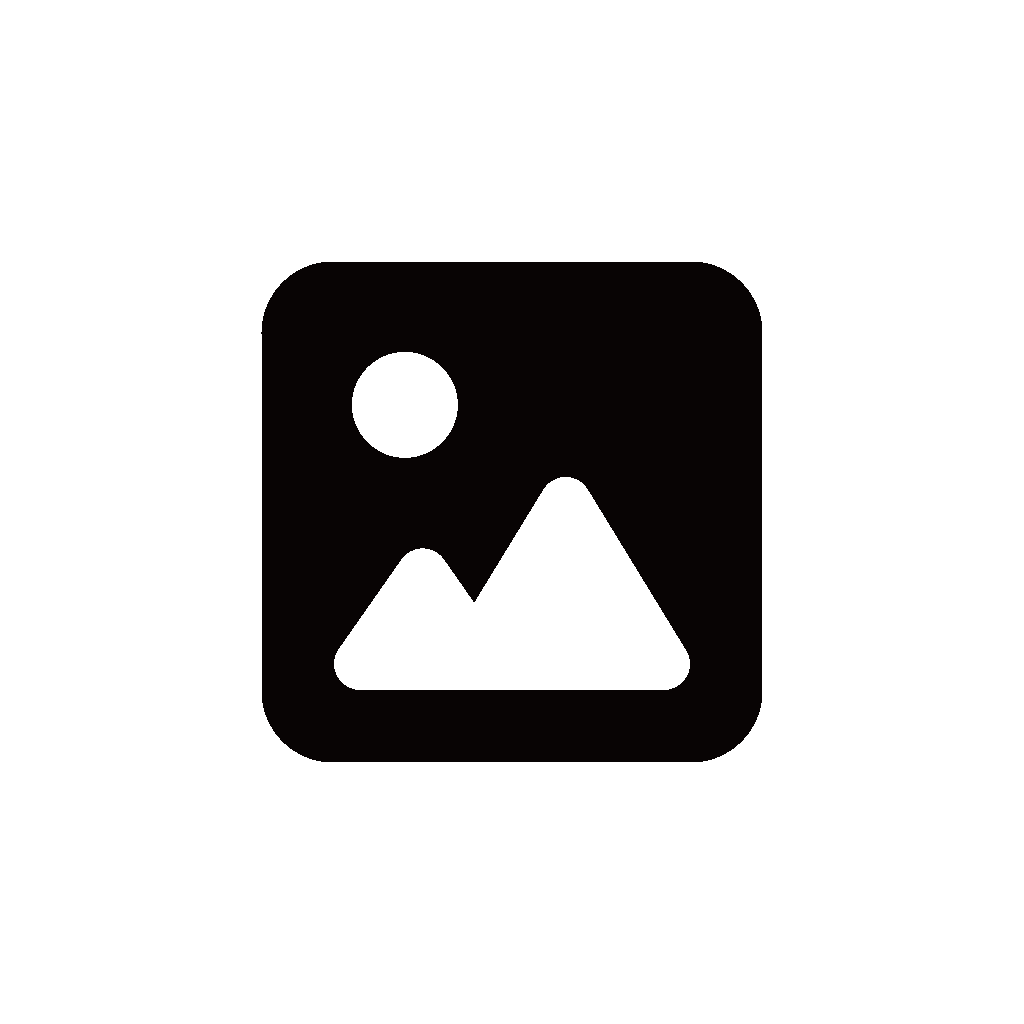 第1駐車場第1駐車場
第1駐車場第1駐車場 -
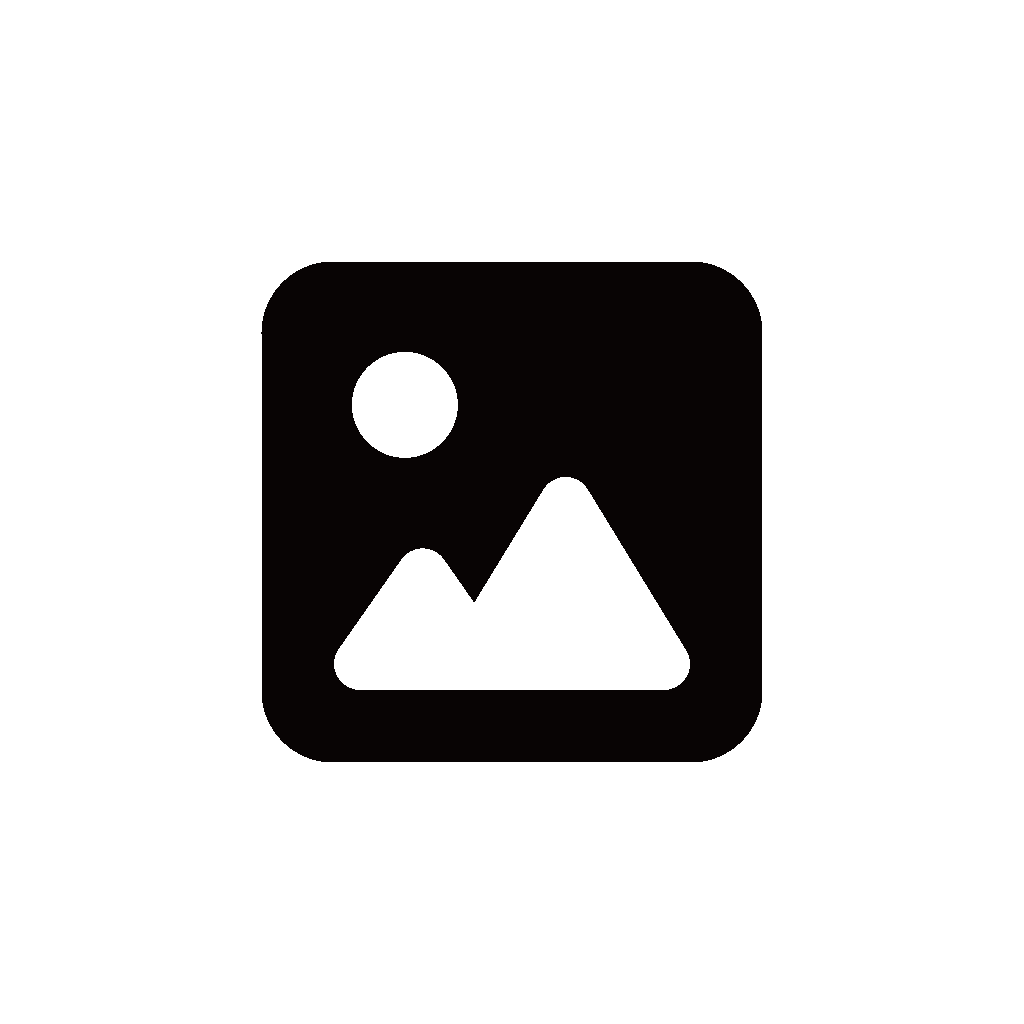 第2駐車場第2駐車場
第2駐車場第2駐車場 -
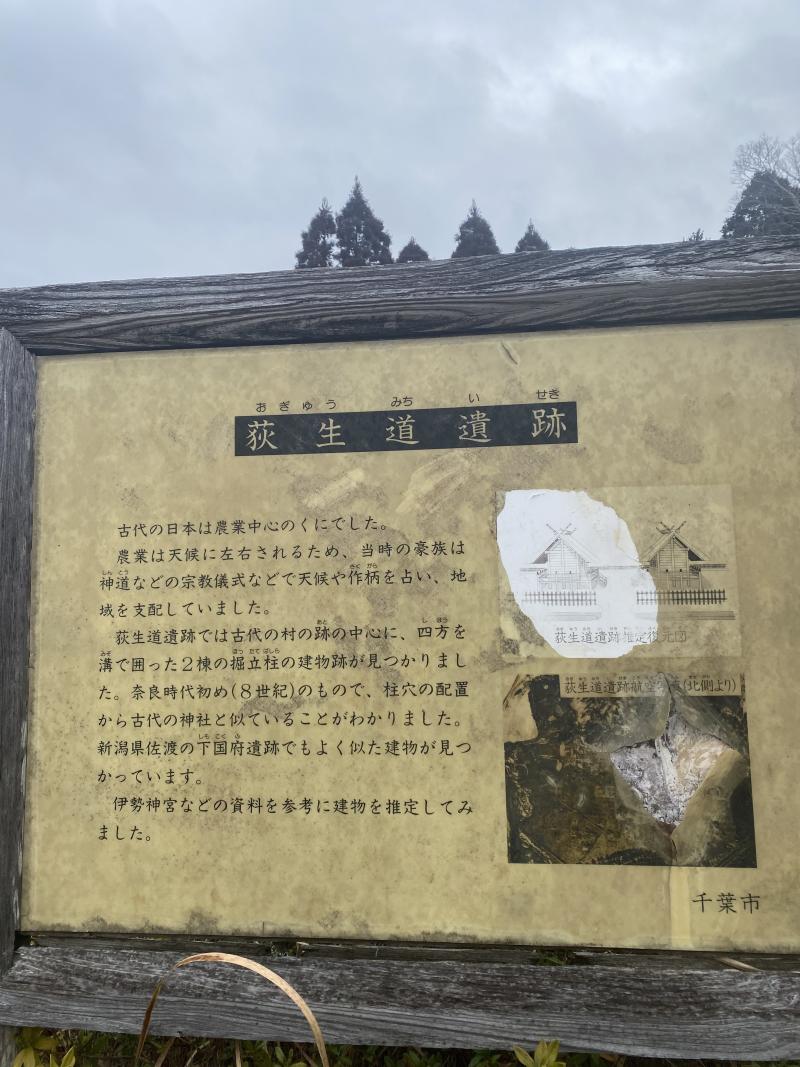 荻生道遺跡(おぎゅうみちいせき)第2駐車場
荻生道遺跡(おぎゅうみちいせき)第2駐車場 -
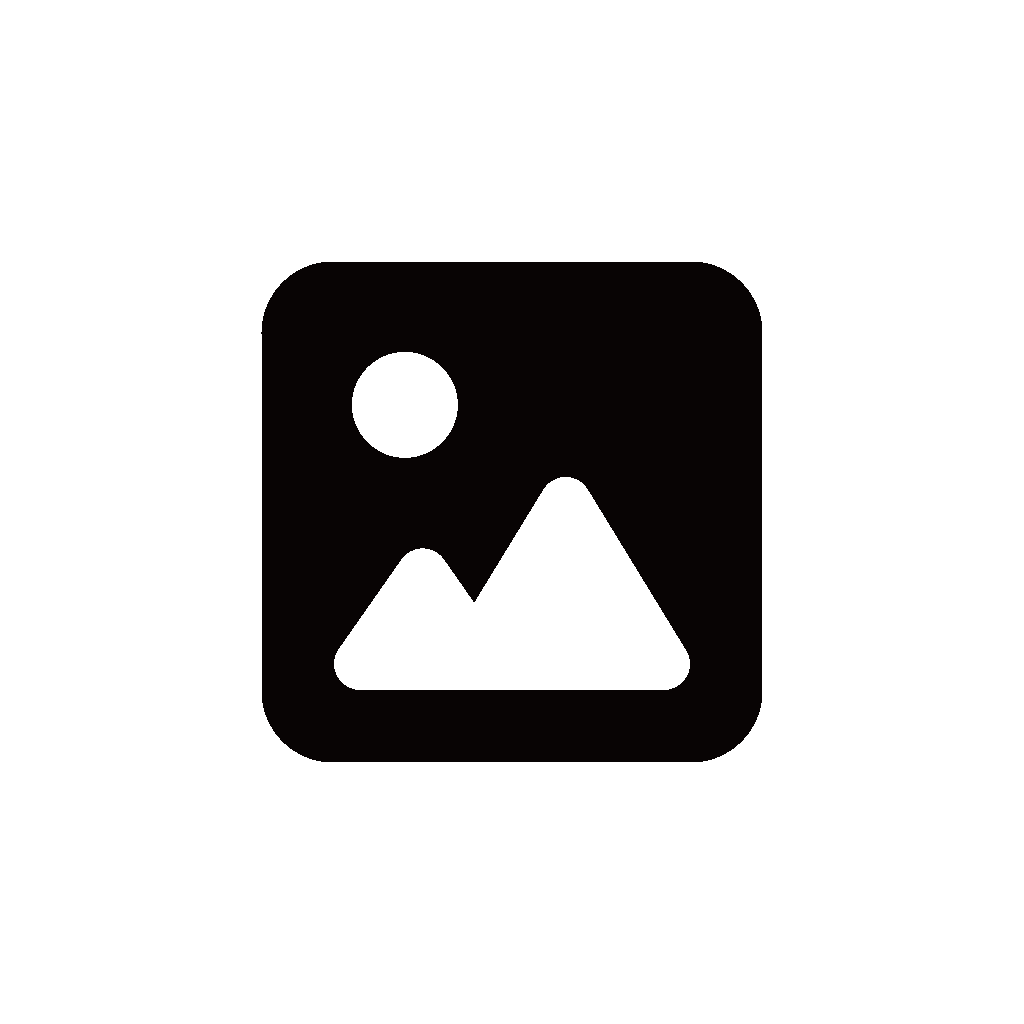 第3駐車場第3駐車場
第3駐車場第3駐車場 -
 小中池
小中池






























